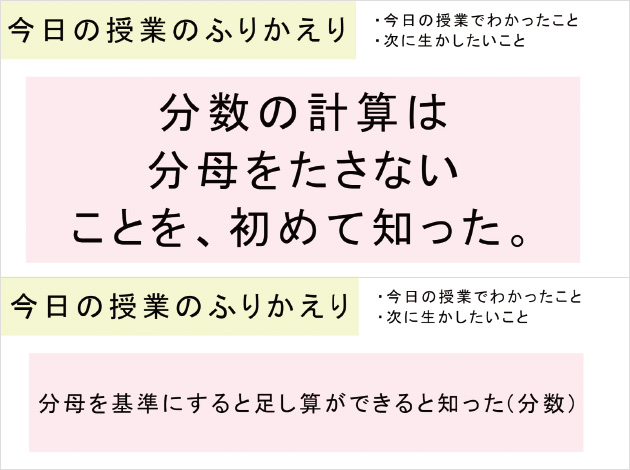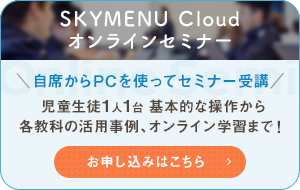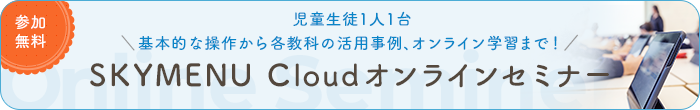そのほかの実践事例
-
![【タブレット端末活用】集めた情報を[シンプルプレゼン]にまとめて上手に発表しよう](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn220599_01.jpg)
小学校4年 国語 SKYMENU Cloud事例
【タブレット端末活用】集めた情報を[シンプルプレゼン]にまとめて上手に発表しよう
佐々木 健視(学校法人成田山教育財団 成田高等学校付属小学校 教諭)
-
![【タブレット端末活用】[資料置き場]を活用!操作を時短化し、鑑賞力を深めよう](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn220706.jpg)
小学校5年 図画工作 SKYMENU Cloud事例
【タブレット端末活用】[資料置き場]を活用!操作を時短化し、鑑賞力を深めよう
久保田 智子(神戸市立若草小学校 教諭、兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科研究生)
-
![【タブレット端末活用】[発表ノート]で、作品を撮影して記録児童の意欲高まり、ねばり強く図画工作の授業で毎時間1人1台端末を活用](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn220916.jpg)
小学校 図画工作 SKYMENU Cloud事例
【タブレット端末活用】[発表ノート]で、作品を撮影して記録児童の意欲高まり、ねばり強く図画工作の授業で毎時間1人1台端末を活用
久保田 智子(神戸市立若草小学校 教諭、兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科研究生)
-
![【タブレット端末活用】個人追究から全体共有へ[発表ノート]と[ポジショニング]の活用](https://www.sky-school-ict.net/file/post/thumb/bn220699_01.jpg)
小学校4年 国語 SKYMENU Cloud事例
【タブレット端末活用】個人追究から全体共有へ[発表ノート]と[ポジショニング]の活用
栁沢 準二(長野県松本市立四賀小学校 教諭)
-

小学校6年 図画工作 SKYMENU Cloud事例
【タブレット端末活用】デジタル交換日記で、学びを蓄積!共有!
久保田 智子 (神戸市立若草小学校 主幹教諭、兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科研究生)