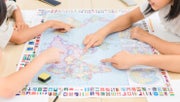変化が激しく、先行きが見通しにくい時代を生き抜くには、予期せぬ事態に柔軟に対応する力が求められます。人と上手に関わっていくことも、長い人生において幸せや成功を手に入れるために必要な力です。このような、これからの社会を生きる上で求められる能力を「非認知能力」といい、近年は早期から非認知能力を高めることの有用性が注目されるようになりました。この記事では、非認知能力と認知能力の違いや、非認知能力が重視される理由についてわかりやすく解説します。
非認知能力とは、意欲や協調性、やり抜く力など、数値では表せない能力のこと
非認知能力とは、意欲や協調性、やり抜く力など、知能検査や学力テストなどで数値化して捉えられない能力のことです。社会情緒的能力や社会情動的スキルとも呼ばれます。非認知能力の特徴として、「何らかの望ましい社会的結果(学業成績、収入、心身の健康など)を予測すること」「測定が可能であること」「介入やトレーニングで変容可能であること」などが挙げられます。
認知能力との違い
認知能力とは、知識・技能、思考力等を含む、知的な能力のことをいい、知能検査や学力テストで測定できる学力や知能が認知能力です。対して、非認知能力はテストや検査で測定できない、目に見えにくい意欲や意志、情動、社会性に関わる能力のことです。
学習指導要領では、育成すべき資質・能力として「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」を3つの柱としています。このうち「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」は認知能力に当たり、「学びに向かう力、人間性等」が非認知能力に当たります。この2つは相互に関連し、一つの活動の中は必ず認知面と非認知面が含まれており、共に育つとされています。
非認知能力の具体例
数値化できないとされる非認知能力は、一般的に自制心や意欲、協調性などと表現されます。これらは、具体的にはどのような力で、どのような場面で役立つのでしょうか。ここでは具体例を挙げて、代表的な非認知能力を紹介します。
ありのままの自分を受け入れる力
自分のことを「好き」だと言える力。つまり、ありのままの自分を受け入れる自己肯定感は、重要な非認知能力の一つです。自分のことは自分が最も近くで見ています。そして、自分自身の良いところだけではなく、悪いところも認識しており、それが自己否定の感情を生み出すことも少なくありません。
自己肯定感は、良いところも悪いところも含め、あるがままの自分の価値を「無条件に」認められることで、この力がすべての行動の土台となるといわれています。自己肯定感が高くなれば、成功や失敗という結果にかかわらず、自分自身の価値を認めることができます。一方、自己肯定感が低い場合には「自分にできるわけがない」「失敗するのが怖い」という気持ちが先立ち、積極的に「やりたい」と思うことが少なくなる傾向があります。
自己肯定感を育むためには、特に幼少期に一番身近な存在である親から愛されることが、最も重要だといわれています。「自分のすべてを受け止めてもらえた」という経験の蓄積によって得られた安心感が、自信につながります。
自らの意志で行動する力
子どもが、何かに夢中になっているときは、非認知能力が働いているときだといえます。子どもが物事に興味・関心を持ち、自らの意志で行動する力が発揮されている状態です。自分の意志で意欲を持って物事に取り組むとき、子どもは大人以上に集中力を高め、試行錯誤や創意工夫を積み重ねます。時には、そばで話しかけた声が耳に届かないほど集中力が高まることも少なくありません。
こうした力が発揮されていると、たとえ自分の期待や想定とは違った結果になったとしても、「なぜだろう?」とその原因を探究し、「どうすればいいんだろう?」と問題解決を図ろうと前向きに考えることができ、何度でも挑戦することができます。こうした、自らの意識で行動する力、夢中になる力は、どこまでも成長しようという意欲に直結する、大切な非認知能力です。
感情を前向きに切り替える力
人は、感情によって判断や行動が大きく左右されます。さまざまな物事に直面した際、自然と湧き上がってくる感情を適切に処理し、前向きに切り替える力。つまり、感情を適切にコントロールする力がとても大切です。ただし、自然と湧き上がってくる感情を力ずくで押さえ込もうとしても、心にゆがみを生じかねません。しかし、思いどおりならないからと怒ったり泣いたりして、感情のままに振る舞うわけにはいきません。
湧き上がる感情と正面から向き合い、今直面する状況をどう捉えればいいのか、どう行動すればプラスになるのかを考えることが、感情をコントロールすることになります。こうした非認知能力が身につけば、困難に直面しても、気持ちを切り替えて対処することができます。
思いやりを持って他者と協働する力
人は社会的動物であるといわれます。多くの人との関わりの中でのみ、生きることができるからです。長い人生のなかで、さまざまな人と出会い、他者と協力し合って物事に取り組む機会が無数にあります。そのとき、相手の気持ちを察して共感する力や、自分の思いや考えを的確に伝える力、異なる意見から新しい視点を獲得する力など、他者と協働する非認知能力がとても大切になります。
非認知能力が高い人が持つ特長とは
非認知能力が高い人とは、前述した自己肯定感や自ら行動する力などを身につけている人ですので、精神的に安定していて、物事に対して主体的な態度で取り組むことができる、状況の変化にも強いという特長があります。また、感情のコントロールがうまく共感性も高いことから、集団の中でリーダーシップを発揮できるタイプの人も多いです。
非認知能力に含まれるスキルと要素
OECD(経済協力開発機構)は、学力や知能を指す認知能力と対になる非認知能力を「社会的情動スキル」とし、「(a)一貫した思考・感情・行動のパターンに発現し、(b)学校教育またはインフォーマルな学習体験によって発達させることができ、(c)個人の一生を通じて社会・経済的成果に重要な影響を与えるような個人の能力」と定義しています。さらに、社会情動的スキルに含まれる能力として、以下の3点を挙げています。
社会的情動スキルに含まれる3つの能力
- 目標の達成(忍耐力、自己抑制、目標への情熱)
- 他者との協働(社交性、敬意、思いやり)
- 情動の制御(自尊心、楽観性、自信)
また、2021年7月に中央教育審議会の初等中等教育分科会に設置された「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」は、「幼児期の学びの特性」として非認知能力が重要であるとしており、意欲・意志・情動・社会性に関わる3つの要素からなるとしています。
非認知能力の3つの要素
- 自分の目標をめざして粘り強く取り組む
- そのためにやり方を調整し工夫する
- 友達と同じ目標に向けて協力し合う
同委員会は、非認知能力が就学前の4~5歳に顕著に発達し、さらに保育者や仲間集団を通して社会に触れて多くのことを学び、学校生活のなかで学童期・思春期の発達を経て、大人へと成長していくとしています。
非認知能力が注目される理由
非認知能力が注目されるようになった背景には、2000年にノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者、ジェームズ・ヘックマンの影響があります。ヘックマンは、1962~1967年にかけて行われた、経済的に恵まれない家庭の3~4歳のアフリカ系アメリカ人を対象にした調査「ペリー就学前プロジェクト」に注目し、分析を続けました。
ペリー就学前プロジェクトは、1960年代にアメリカ・ミシガン州において行われた就学前教育の社会実験で、非認知能力に重点を置き、「質の高い幼児教育プログラムに参加したグループ」と「参加しなかったグループ」を対象に、長期にわたり追跡調査を実施しました。ペリー就学前プロジェクトでは、質の高い幼児教育プログラムへの参加が、その後の「学校の良い成績」「より高い収入」などにつながっているという結果が出ています。
ヘックマンは、経済学者としてこのプロジェクトをさらに研究し、幼児期の非認知能力の習得が人生そのものに大きな影響を与えることを明らかにしました。非認知能力の育成は、子どもたちが雇用や収入を得て経済的に成功を収めるだけでなく、幸せな人生を送るためには、学力や知能といった認知能力よりも「目標の達成に向けた情熱や忍耐力」「他者を思いやり、敬意を持って接することができる社交性」「自分に対する自信」といった非認知能力が重要であることを示したのです。
非認知能力の育成に効果的な探究学習
前述のとおり、非認知能力の発達は気質差、個人差が大きいですが、特に幼児期(4~5歳)に顕著な発達が見られ、学童期・思春期の発達を経て、大人に近づきます。そのため、子ども時代に非認知能力を育成できる環境に身を置くことが大切だといわれます。その意味でも「主体的・対話的で深い学び」は、非認知能力の育成に効果的だといわれています。特に、子どもの自発的な学びを育む「探求学習」は、非認知能力の育成につながるとして注目されています。
探求学習は、変化の激しい社会に対応し、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目標にしています。児童生徒自身が課題や目標を設定し、情報を収集・分析したり、周囲を巻き込んで協働したりしながら解決に向けて活動するため、目標のために努力する力や耐える力、コミュニケーション能力、自尊心の向上といった非認知能力を高めることにつながります。
幼少期の非認知能力の育成が重視される今、幼児期から学童期にかけて取り組む「主体的・対話的で深い学び」、中でも探求学習は、ますます重要になっていくと考えられています。
未来を生きる子どもたちの非認知能力を育もう
ヘックマンの研究結果からもわかるように、生涯にわたるウェルビーイング(身体的、精神的、社会的に満たされた状態)を手に入れるには、幼児期から学童期にかけての非認知能力の育成が重要です。幼少期の教育によって育成された非認知能力は、認知能力よりも子どもの長期的な成果に影響を与えるという研究も蓄積されてきました。人生を安定させる土台として、また、周りの人に愛される人間としての基盤として、子どもたちの非認知能力の育成に取り組むことが求められています。
ICTを活用した学習活動を支援する「SKYMENU Cloud」
GIGAスクール構想によって、児童生徒1人1台の端末が配備され、ICTを基盤とした新しい学びのかたちが広がっています。児童生徒が自己調整しながら学びを進める「個別最適な学び」と多様な個性を最大限に生かす「協働的な学び」、これらの学びを一体的に充実させ、児童生徒が自らの手で未来を豊かに創り出していく力の育成を「SKYMENU Cloud」は支援します。